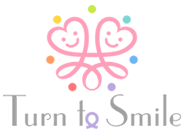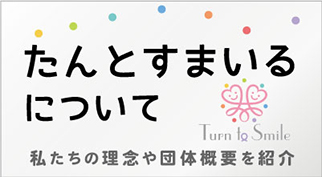「学ぶことの責任について」
(1)夫:30代(会社員、関東地方在住)
(2)妻:30代
(3)子:なし
(4)既婚or未婚:離婚
(5)同居or別居:別居
(6)プログラム参加期間 :4年5ヶ月
1. パートナーとの出会いと関係の変化
19歳の時、私はパートナーと同じ大学のサークルのメンバーとして出会いました。今でも覚えている最初の印象はとても田舎っぽい女の子で、私は「絶対付き合うことはないのだろう」という事を考えていました。DVについての学びをしている今だから思う事ですが、女性と出会った瞬間に付き合うことの「アリ」「ナシ」を考えてしまっている時点で、女性のことを軽視していたし、私のDVはもう始まっていたのだろうなと思います。そんな第一印象だったので付き合うことがなさそうだと思っていた私でしたが、その後のサークル活動を通して、パートナーの純粋なところや嘘がつけないところ、そしてなにより私の話を真剣に聞いてくれたことに惹かれ、彼女の事が好きになりました。これ以前の私は両親に対して、「認めてもらえない」「話を真剣に聞いてくれない」という思いが強くあったので、そんな自分を彼女は受け入れてくれたように感じたのです。私から告白をし、それからの大学生活の4年間のお付き合いした後、私が他県の大学院へ進学した後の6年間は遠距離恋愛をしておりました。
私は大学院受験をして、他県にある少しレベルの高い研究所の研究室に所属することになりました。そこから私の状況は少しずつ変化していったと思います。研究という性質からか、他人と議論を交わす事があります。その際に自身の研究内容や研究結果を他人の批判から守らなくてはなりませんし、また他人の研究結果についても同じように批判しなくてはなりませんでした。私は最初、それがとても苦手で、うまく批判することも批判から守ることもできず、指導教員に怒られる日々が続きました。しかし、人間は順応するもので、私はそう言った研究を議論するための話し方や、やりとりにも慣れていきました。それができるようになればなるほど、私のパートナーへの接し方は、このこの研究のやり方と同じように、変わっていきました。というのも、パートナーの主張を論破し、自分の主張には批判する隙を与えないような喋り方になっていきました。パートナーは自己主張が得意ではないのにも関わらず、私はこの手法を使ってパートナーを自分の思い通りに動かそうとしていました。研究の様な対等な立場での議論ではない場面でその手法を使い、私の主義主張の押しつけになっていったのです。今思うと私のパートナーへのコントロールはこの時から始まっていたのだと思います。
パートナーは地元の大学院に進学していたのですが、精神的な理由から大学院に通えなくなってしまいました。当時は休学理由は彼女が研究の現場に対して水が合わなかったからだと思っていましたが、今考えると、私との関係性や遠距離であったこと、私の接し方が変わっていったことと無関係ではないと思います。そこから1年間の休学を経てパートナーは退学後、就職をしました。その間ずっと私はパートナーに変わる事なく接して、『病気で辛い時期を自分が支えた』と思っていました。この思考が後に説明しますが、私の暴力を私自身が容認した、まず最初の理由になってしまいました。
2. 私が身体的DVに至るまで
パートナーが会社に勤めるようになって数年後、私の大学院の集大成である博士論文の執筆の時期がやってきました。博士論文の執筆が自分の人生で一番の課題であると思っていた私は、その期間は自分自身の事でいっぱいいっぱいになってしまうであろうと考えていました。自分に余裕がなくなったら彼女を支えるどころか、彼女に頼ってしまうかもしれない。そんな状況で彼女が私と恋人関係でいてくれるか不安でした。それでもパートナーと別れたくなかった私は、先にプロポーズをして承諾をもらい、関係を確固たるものにしようと考えました。今思えばプロポーズの言葉も非常に自己中心的で、「自分がパートナーを幸せにできるかはわからないけれど、自分の幸せのためにはパートナーが必要だから、結婚してください」というような事を言いました。それでもその時はパートナーが泣いて喜んでくれたのを、今でも覚えています。
そんな状況で博士論文に挑んだ私ですが、月日が流れるにつれどんどん精神的に病んでいきました。研究がうまくいかない、人間関係もうまくいかない、なにもかもうまくいかないように感じていました。大学のスクールカウンセラーに勧められ精神科を受診し、うつ状態の適応障害であるという診断を受けました。そこから自分のパートナーへの依存はどんどん酷くなっていきました。しまいには研究のメール一通送るのでさえ、パートナーに相談しないとうまくできない自分になっていました。そんな自分を心配して、「博士論文が通ってから結婚する」予定を早めて、パートナーが上京し、転職までしてくれて結婚しました。彼女はこの時、結婚したら私の精神状態が良くなると思ってくれていたようでしたが、私の状況は悪くなる一方でした。博士論文は提出はしたものの一人の審査員の先生が合格を出さず、1年以上に渡り修正が続きました。そんな状況の私は病院にもカウンセリングにもパートナーに付き添ってもらって生活を続けていました。この時の私の心境は、パートナーに感謝するのではなく、精神科に適応障害と診断されたことを理由に、『前回パートナーが病気の時、支えたのは自分だから、今度は自分が支えてもらう番だ』と思っていました。そんな生活がうまく行くはずもなく、私は自分の博士論文がうまくいかない八つ当たりを彼女にするようになりました。そして、口論の末、彼女のほほにビンタをしてしまいました。当時の私はそれに狼狽し、すぐに謝罪をしました。彼女はそれを受け入れてくれましたが、二度とやらない約束をしていたのに、結婚生活中、二度もそれを繰り返してしまいました。さらにその時の私はもっと自分勝手な事を考えていて、彼女と別れたいとは微塵も考えていないくせに、「彼女は素晴らしい人で私なんかと一緒にいたら幸せになれない。私が叩くことで、彼女が私から離れていけばそれで良いのだ」と矛盾した考えを持っていました。それくらいパニック状態でしたが、自分が自分の行為を正当化する理由を一生懸命考えて、自身の中に支離滅裂な論が出来上がってしまっていました。
別居が決定的になった日も結局は私の八つ当たりでした。博士論文が完成に近づいたある日、私は次の研究職のポストに応募するための書類づくりをしていました。その作成のために必要な書類がどこにあるのか、最初は彼女に聞いただけのつもりでしたが、「そんな書類は知らない」という彼女の言葉に私が腹を立て、怒鳴ってしまったことが最後でした。結局その書類は私の実家にしまってあり、知らないという彼女の主張は至極真っ当で、完全なる私の八つ当たりでした。こうした私の八つ当たりに耐えられなくなった彼女と、口論になったこの日に別居をする事が決まりました。そこからは、一度だけ話し合いの場はありましたが、それは彼女が別れたいということを私に伝えるためだけで、特にやりとりすることもなく私の元に離婚届が送られてきた、ということになります。
3. 二人の関係性の中にあったDVの連鎖
今から思えば、私がした暴力は手を上げてしまったことだけでなく、お付き合いをしていた当初からパートナーに依存し、パートナーを支配したい欲求に基づく精神的な暴力も多かったように思います。大学院時代は遠距離で電話することが多かったのですが、口論になると私が納得いくまで何度も電話をかけました。それは正当な話し合いではなく、私が納得するまで電話を切らせないで話し続けるというものでした。自分がいかに正しく、彼女がいかに間違っているかを延々と話し続けてしまいました。その電話口で彼女が謝っても、「本心でない」などといちゃもんをつけ、延々と彼女の時間を奪っていたと思います。そんな私に嫌気がさした彼女は、私の電話番号を着信拒否し、何か月も連絡が取れなくなった事もありました。そういう場合、私は、いかに自分が愚かであったか、いかに自分が反省しているかを長々と手紙を書き、彼女に送りました。そんな彼女がまた私を信じてくれて、再び連絡を取り合うようになる、という事を何回も繰り返していました。これがまさに暴力のサイクルから抜け出せなくなっていた常態だったと、今となっては思います。
実は、一番最初に手を出してしまった時に、これはDVに相当するし、自分一人でなんとかすることは難しいと感じていたので、Webで調べたDVの加害者更生プログラムに参加することをパートナーに提案していました。しかし、パートナーはDVだとは思わないこと、それよりも博士論文を頑張ってほしいという事、を言われ、参加を見送ってしまっていました。あそこで自分が更生プログラムに参加していたらという後悔はいまだに残っています。明らかに私の行動はDVのそれでありましたが、それをDVと判断できないほどパートナーを追い詰めてしまっていたのだと今となっては思いますし、彼女自身もDVと分かっていながらそれを認める事にとても大きなハードルがあったのではないかとも思います。それくらい暴力というのは被害経験者の方の判断力を奪ってしまうものだという事です。
4. 離婚できるようになるためのプログラム参加
そうした経緯から別居状態になり、選択肢は離婚以外あり得ないという状況になってしまいました。自分に非があること、パートナーの希望を叶えるためには離婚するしかないということは頭では理解していましたが、一人でそれを受け止めて離婚届にサインすることが難しいと考えて、「離婚」を受け入れられる様になる事を目的にグループに参加しました。そういった参加目的から、最初に参加したグループから「振り返り」を行い「皆さんにボロクソに言ってもらおう」と思っていました。なので、グループに参加する不安や心配はさほど大きくはありませんでしたが、プログラムの理念である「自分を変えるため」に参加した訳でもありませんでした。
グループに参加した皆さんに現状をお話ししたところ、「離婚届を受け取っているのにサインしない理由がわからない」であったり、「離婚しないことが暴力になっていて今もDVを続けていることを自覚したほうが良い」とコメントを頂きました。しかしながら、グループに入った当初は、それでも離婚を受け入れることができませんでした。そこから離婚届にサインをして返信するまでに半年の時間を費やしてしまいましたし、離婚届を返信した後もパートナーに連絡を取ろうとしたりと、『離婚しないことによる暴力』を続けてしまっていたと思います。
離婚が成立してからも、休み休みではありましたがグループには参加していました。それは最初に述べた通り「自分が変わる」事を目的にしていた訳ではなかったので、惰性でグループに参加している状況が約2年ほど続いていたかのように思います。その期間、私は、離婚して独りになって「悲しい」、「辛い」だけしか考えることができませんでした。「自分を変えると言ってもそんなこと簡単には出来ない」と思っていたし、何より「あれだけ酷い事をした自分が、前向きに楽しくすることが間違いだ」と思っていました。自分が大好きなパートナーを傷つけて暴力を振るったこと、それを自覚すればするほど自分の事が許せなくなるし、自分を許さず辛くしていることで、勝手に自分が暴力の罪を償っている気になっていました。それは、自分に罰を与えることに依存していたのだと、今は思いますが、当時はそう考えることでしか自分を保つことができませんでした。誰も、もちろん私のパートナーも望んでいる訳ではないのに、自分が今辛く苦しいのは罰で、その罰があるから自分はなんとか生きていけるものだと思っていました。なので、グループに行く意味も、そして行かない意味も見出す事ができずに、ただ日々を過ごしているという時間が続いていました。
5. プログラムで学ぶ意味
参加者のほとんどの方は別居していても、離婚していても、パートナーとの関わりがあります。そんな中、離婚以来パートナーとまったく連絡をとっていない自分は、グループを辞めるタイミングを失ってしまっていたと思っていました。そんな自分を変えるキッカケをくれたのも、まさにグループの参加者の方とのやりとりを通してでした。曲がりなりにも1年以上はグループに参加していたので、暴力についてはいくつか学んだ事がありました。それを新しくグループに入ってきた方が「振り返り」をしてくださった場面などで自分の考えをお伝えする機会が何度もありました。その数ヶ月後にその時の「振り返り」をしてくださった参加者の方から、「私の言葉が自分を変えるきっかけになった」と言っていただける機会がありました。その言葉に、自分が苦しくてもやってきたことに意味があったと思えたことが、自分の中で大きな気づきになりました。また、Covid-19の影響でグループがZoom参加になった時に、長く学んでいるけれどまだ加害行為に苦しむプログラム参加者との出会いがありました。その方の暴力の告白や、それを手放すことを誓った「振り返り」を聞いたことが、私にとってとても衝撃でした。自分がしてしまったことを文章にしたこと、それをグループの仲間や彼の友人たちに告白したこと、とても簡単ではなかったと思いますし、彼が自分と多くの時間を向き合ってきたことを感じました。そもそもの学びの姿勢で彼と私には大きく差がありましたし、彼が自分がしたことと本気で向き合って解決しようとしていることが伝わりました。そうして変化した、あるいは変化したい人たちに対して、自分の学びの姿勢を恥じたのが、自分を変える最初のきっかけになったと思います。
そういった経験から私は「学びの責任」について考えるようになりました。私は自分がしたことが暴力であったこと、暴力は人の人生を奪ってしまう行為であることを知らなかった状態から、今はもう知ってしまった状態にあります。もう知らなかった状態には戻れないし、知った以上、それを繰り返さないし、繰り返させない責任が自分にはあると感じました。また、長くグループに通っている人間として、自分がグループに参加することで、『何か変わった事』を示さないといけないのではないのか、と考えました。なので、今は、自分を変えたい、自分を変える、という思いをもって本気で学んでいるし、グループの活動に取り組んでいます。この体験談を執筆しようと思ったのも、自分が次のステップに行くために必要な事だと思ったから、です。
6. 学びの責任を果たすために
私がグループでの学び以外で気をつけていることがいくつかあります。まず、自分の状態を常に考えて、自分が良い状態になれるよう、自身の欲求充足を自分でするようにしていることです。私はパートナーに依存して、自分で自分の機嫌を取るということは考えていませんでした。また研究に集中するがあまり、いろんな趣味の活動を辞めていった経緯があります。なので、少しずつ、自分にとって楽しいことはなんなのか、何が気分転換になるのか考えながら、自分の機嫌をとっております。最近では趣味が高じてグループの参加者の方と交流のためのゲーム大会などを開けるようになるまでになりました。
次に気をつけていることは、頼れる先を少しずついろんな人に分散することです。私は両親との折り合いが悪く、研究で大変になった時に両親を頼ることができませんでした。それが全てパートナーへの負担になってしまったと思います。そこで、友人やカウンセラーにもいろいろな事を相談するように気をつけています。もちろんグループの参加者にも自分が困ったことがあったときには相談させていただいています。一人に依存しなくても少しずつ負担にならない範囲で、人間関係を築いていきたいと今は思っています。
最後に、どんな人であっても丁寧な言葉遣いは忘れないことを、気を付けています。仕事の同僚であっても、年下であったとしても、フレンドリーな敬語調で話すように気を付けています。私が研究時代に使っていた、相手を批判したり論破したりする話し方ではなく、相手をリスペクトした話し方になるよう気をつけています。私は自分が「喋る」言葉が、自分が一番「聞く」言葉でもあると思います。自分を取り巻く言葉が変われば、それは自分を変えることに近づくのではないかと思っています。
7. 最後に
そうした学びを続けていったおかげで、いくつか環境が変化しました。私は研究を辞めて一般企業に転職をしたのですが、そこの同僚の方からは、「僕の人生で出会った中でトップクラスに優しい人」と言ってもらえる機会がありました。また、ゲームのつながりがある友人からは、「怒らない」「イラつかない」ねと言ってもらえるようになりました。これはグループに参加してから後に出会った人たちですが、自分が以前のままだったらそういう事は言ってもらえなかったと思います。
またまだ全員ではありませんが、パートナーとの共通の友人の何人かに、私が暴力を振るってしまったこと、それが原因で離婚になったこと、今更生プログラムに通っていること、を告白することができました。友人の中にも葛藤があったかと思いますが、受け入れてもらうことができました。まだ話す事ができてない友人たちにも少しずつ告白できるように、学びを続けていきたいと思っています。
最後になりますが、私は今、パートナーの幸せを心の底から願っております。私がパートナーと共に人生を歩む事が出来なかった事はとても残念ですし、その前にパートナーの人生の貴重な時間を奪ってしまったことはとても申し訳なく思っています。そんな自分が今できることは、自分を変え続ける事だし、パートナーの人生に今後関わる事がなくとも、パートナーの幸せを願うことだけだと思っております。そのためにも、学び続けることを、ここに誓いたいと思います。
一般社団法人 Turn to Smile たんとすまいる
東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2F
MAIL:info@turn-to-smile.org
平日: 10:00~18:00
(面談時間 月・木・金:21:00)
土日祭日: お休み
※面談中のために応答出来ない場合がございます。
その場合は、お手数ですが改めてご連絡お願いいたします。