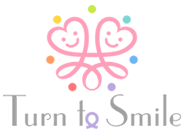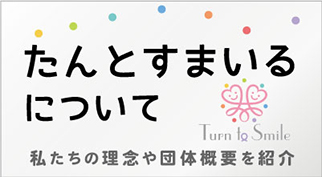「みんなに支えられて生きている」
(1)夫:30代(公務員、関東地方在住)
(2)妻:40代
(3)子:女1人
(4)既婚or未婚:離婚調停を経て離婚
(5)同居or別居:別居(ただし、ほぼ毎日会っている)
(6)プログラム参加期間:約4年
Ⅰ はじめに
今から約4年前のことです。《妻さん》と《娘さん》は、私のDV・虐待を理由として、3人で住んでいた家から避難しました。私が、DV・虐待の加害行為をしていたと自覚し、DV加害更生プログラム「たんとすまいる」で学び始めたのは、その時からです。
プログラムでの学びを通して、私は、自分自身を根本から見つめなおし、変えていく必要があると実感しました。そして、日々、自分自身を変える営みを続けました。
それから約4年が経ちました。おかげさまで、《妻さん》と《娘さん》と私との関係も、少しずつより良いものになっています。今、私は、《妻さん》と《娘さん》と、ほぼ毎日一緒に過ごさせてもらい、これまでで一番幸せな関係を築かせていただいていると実感しています。
今の状態に至るまでの、私の体験談を記していきます。
Ⅱ 私が犯してきたDV・虐待
【DV・虐待につながる価値観】
《妻さん》とは、私が学生だったときに知り合い、就職する前後に結婚しました。
私は平成生まれですが、後に《妻さん》に聴いてみると、私を見て「昭和の男だ」と思ったそうです。「価値観が古い」と感じたからだそうです。
実際に私は、こんな価値観を持っていました。
・「夫は稼ぐから、妻は専業主婦でよい。」
・「妻は働いてもいいけれど、それは家事や育児を完璧にこなした上でないダメだ。」
・「妻と私はいつでも一緒にいないといけない。妻が週末や夕方以降に私以外の人と会うのは、私を尊重していないから許せない。」
・「子どもは厳しくしつけなければいけない。子どもを叩くこともあるけれど、それは愛のムチだから許される。」
今振り返ってみると、DV・虐待につながる価値観ばかりでしたが、当時の私は、これが唯一正しい価値観だと思っていました。そして、こうした価値観を共有しない《妻さん》に対して、「相手の方が間違っている」と思って、非難していました。
ではなぜ、私は、以上のような価値観を持っていたのでしょうか。「私自身が育った家庭が、そのような家庭だったから」というのが、私にとって答えです。
私自身が生まれ育った家庭では、母親は、幼い頃の私の目から見て、家事や育児を完璧にこなしており、その上、パート勤務もしていました。週末は家族で過ごすことが基本で、父親は家族の者以外と過ごすことを嫌がりました。また、しつけと称して、私は父親から叩かれて育ちました。私は、こうした家庭で育つ中で、(成績が悪いと叩かれるので必死に勉強した結果、)トップクラスの成績を保持するようになりました。そして、「高学歴」とされる大学に入り、「社会的に地位が高い」とされる仕事に就きました。
私は、以上のような人生経験の中で、
・「自分が生まれ育った家庭の価値観は正しいのだ」
・「だから、自分が妻と築いていく家庭も、自分が生まれ育った家庭のようにしていくべきだ」
・「そうした価値観を、妻は共有するべきだし、共有しているはずだ」
と強く認識するようになりました。
なお、この点に関連して、プログラムでの学びで印象的だった内容があります。それは、「生まれ育った家庭でDV・虐待につながる価値観があったことは、自分がDV・虐待を犯してよい理由にはならない」ということです。私は、DV・虐待ではない行動を選ぶことができます。そうである以上、自分の加害行為について、自分の生まれ育った家庭環境のせいにする(責任転嫁する)ことはできない、ということです。この点は、これまで責任転嫁をたくさんしてきた私が自身の過去をふりかえる際に、特に注意したいと思っている事項です。
【DV・虐待の実際】
結婚した当初から、《妻さん》との間ですれ違いがありました。実際は、「すれ違い」ではなくて、私がDVをしていただけなのですが、当時の私は、それを「すれ違い」、「価値観が違うだけ」だと思いこんでいました。
例えば、私は、「モノを投げる」というDVをしていました。気に入らないことがあると、モノを投げて怒りを爆発させるのです。
私が初めてモノを投げるDVをした時、《妻さん》はとても驚き、私の前で哀しそうな様子を見せました。これに対して、少し落ち着きを取り戻した私は、「ごめん、もうしない。」と謝っていました。しかし、それは表面上のもので、本心ではありませんでした。心の中では、「モノを投げたのは悪かったかもしれないけれど、そもそもの原因は、遅くまで外出している《妻さん》にある」と自己正当化したり、「自分が生まれ育った家庭では、これぐらいの暴力的行為は、許される範囲だった。だから大丈夫なはず。」と育ちの違いのせいにしたりしていました。
また、私は《娘さん》に対しても虐待を行っていました。
先に触れたように、私は暴力のある家庭の中で育ち、勉強がとてもできるようになりました。そうした中で私は、「自分も暴力を受けてきたが、成績は良かった。だから、《娘さん》に対しても、厳しくしつけたほうが良い」と考えていました。
例えば、《娘さん》がお出かけ先の本屋で泣いたとします。すると、まず私は「静かにしな。」と怖い声ですごみます。そして、それでも《娘さん》が泣き止まないとなると、「うるさい!」といって頭を叩き、そして、無理やり《娘さん》の手を引っ張り、外に連れ出していきました。《娘さん》の腕が脱臼したこともあります。
こうしたDVや虐待をしている中で、《妻さん》や《娘さん》は、私に対して怯えるようになり、笑顔が消えていきました。
《妻さん》と《娘さん》から笑顔が消えた原因は私にあります。しかしDV・虐待をしていた当時の私は、《妻さん》と《娘さん》に対する否定的なイメージを持っていました。なので、「オレの前で笑顔がないのは、《妻さん》と《娘さん》がオレのことを大事に思っていないからだ。けしからん。」と思い、さらに怒りを増幅させていました。
Ⅲ プログラムに通うきっかけ
「《妻さん》と《娘さん》との関係は最悪だ。しかし、その原因は《妻さん》と《娘さん》にある。」
そんなふうに思いながら、日々を過ごしていた私が、その見方を180度変えるに至った出来事がありました。今から約4年前のことです。
ある日、仕事から家に戻ると、《妻さん》からの置き手紙があり、「弁護士の連絡を待ってください。探さないでください。」とありました。どうやら、《妻さん》と《娘さん》は、家から避難した(出ていった)ようでした。
私は、「オレに事前に相談もなく、いきなり出ていくなんて、ヒドイじゃないか!」、「やりやがったな!」と怒りに震えました(プログラムに参加したことで、「DV加害をする私に、《妻さん》が「事前に相談」することは難しかっただろう」と想像できるようになりましたが、当時の自分は、「(家族のことはオレが中心で決めることなのに)事前に相談がなかった」ということに対して、激しい怒りを覚えていました)。
私は、怒りで身体が震えながら、近くのスーパーにビールを買いに走り、浴びるように飲んで寝ました。
翌朝。目覚めても、現実は変わりませんでした。私は職場に電話して、急きょ仕事を休むことを伝え、その日には近くの弁護士事務所に相談に行きました。「戦闘モード」になった私は、弁護士に対し、「妻と子どもが出ていった。妻に原因がある。離婚は仕方ないにしても、せめて子どもの親権を取りたいと考えている!」とまくしたてました。
しかし、弁護士との相談を終えて家に帰り、少し冷静になってくると、私の頭に、こんな思いが浮かびました。
「《妻さん》と《娘さん》は、そもそも何で、家から出ていったのだろう?」
私は、インターネットで「妻 家出 原因」などとキーワードを入れて検索してみました。すると、「DV」という言葉が幾つも出てきました。
私は、「まさか自分が」と呆然となりました。「自分がDVをしていたなんて、ありえない!」と否定しようとしましたが、DVについて調べれば調べるほど、自分が該当している気がしてきました。
《妻さん》に原因があると思っていたが、まさか自分に原因があるとは!
私が今するべきは、弁護士を立てて「闘う」ことではなくて、まずは自分自身が変わっていくことではないだろうか?
私は、「とにかく何とかしなければ!」と必死で加害更生プログラムを調べ、幾つかあるプログラムの中から、「たんとすまいる」にたどり着きました。
Ⅳ プログラムに通い始めたころの私
「たんとすまいる」の主宰者との面談を経て、《妻さん》と《娘さん》が家から避難した翌週には、プログラム主宰者との3回の基礎講座を経て、グループへの参加を開始することになりました。
私は、グループに参加し始めましたが、最初からグループでの学びに対して正面から向き合えたわけではありませんでした。
何とかしなければとワラをもすがる思いで参加を開始したのですが、心の片隅では、
「本当に自分はこのグループで、DV・虐待をしない自分に変われるのだろうか?そして、たとえ変われたとしても、《妻さん》と《娘さん》は、私の変化を信じて再同居してくれるのだろうか?もしも信じてくれず、離婚ということになれば、私が変わろうとする努力は無駄なのではないか?」
といった想いも抱えていました。
グループで学ぶ良いことの一つは、自分が抱えている悩みを当事者同士でシェアし、フィードバックをいただけることです。私が、グループに通い始めてしばらくしてから、上記の悩みについて話をすると、グループ参加者(Zさんとします。)の一人から、こういった言葉を投げかけていただきました。
「離婚したからといって、それで人生が終わるわけではありません。養育費を納めるという形で、関わっていくこともできます。今すぐは難しくても、今後《妻さん》や《娘さん》と会う機会だってあるかもしれません。会ったときに、今までと変わらずにDV・虐待を続けるようなTankeさんでありたいですか?それとも、DV・虐待を手放し、より良い人間関係を築こうとプログラムで学び続けている自分でありたいですか?」
Zさんの言うとおりです。
私は、「今こそ自分自身の生き方が問われているのだ!」と感じました。
たとえ離婚したからといって「おしまい」ではありません。その先も人生は続きます。自分がDV・虐待を手放し、良い自分に変わっていくことで、この先の人生をよりものに変えていけるかもしれません。
とにかくやってみなければ、何も変わらないのは目に見えています。「自分にできる目の前のことに集中して、まずはとにかくやってみよう!」、「結果は後からついてくる!」という前向きな気持ちを持つことができました。
Ⅴ プログラムでの学びの内容
私はプログラムで、多くの学びを得ました。この中で、私が特に気づきを得られたと感じている事項を二つ紹介します。
一つ目は、「自分の持っていた「~~すべき」という価値観を、私は手放すことができる」ということです。
私は今まで、《妻さん》や《娘さん》に対して、「~~すべき」という価値観をたくさん押し付けていました。そして、そうした「~~すべき」が達成されないことに対して、怒りを覚え、DV・虐待行為を犯していました。例えば、こんなふうにです。
・「《妻さん》は家事や育児を完璧にこなすべき。完璧にこなせないのに、外で働こうとするなんて、許せない!」(精神的DVをする)
・「《娘さん》は私の子どもなのだから勉強ができるようになるべき。勉強ができないのに遊んでいるのは、たるんでいる!」(心理的虐待をする)
以前の私は、自分が抱く「~~すべき」という価値観は世の中にとって普遍的な正解であり、これ以外の価値観は間違っていると思っていました。
しかし、プログラムで学ぶ中で、自分が持っている「~~すべき」という価値観は、唯一絶対のものではないことを知りました。
・「2、3日掃除をしなくても、汚くて死んでしまう、ということはないですよね?」
・「家事や育児は、《妻さん》任せにせず、自分自身も担っていくことができますよね?」
・「勉強ができるか否かで、人間の価値は変わらないですよね?」
・「生まれてきたときは、《娘さん》がただ生きていてくれるだけで幸せだと感じていましたよね?」
こんなふうに自分自身に問いを投げかけることで、「あれ?今まで自分が持っていた「~~すべき」は、もしかして別のように考えることもできるのかな?」と思えるようになってきました。
「~~すべき」という価値観を手放していくと、私は、「怒り」を覚えることが目に見えて減っていきました。それどころか、自分が今まで持ち合わせていなかった様々な考えを持てるようになり、「~~すべき」から解放されていく中で、どんどん楽になっていく感じがありました。「~すべき」を手放すことが、DV・虐待行為をしない自分に変わっていく第一歩だと感じました。
二つ目は、《妻さん》や《娘さん》の「良いところ」に注目できるようになったことです。
DV加害更生プログラムに通い始めてすぐの頃、「たんとすまいる」の主宰者と個別面談をしているときに、「《妻さん》の具体的にどんなところが良いと思ったの?」と聞かれたことがありました。
その時私は、「はた」と困ってしまいました。
「全部です」と取り繕って言ってみたものの、「具体的に良いところを教えて?」と問われると、全然浮かんできません。私は、これまでの自分がいかに《妻さん》や《娘さん》を否定的なイメージで捉えていたか、いかにそれぞれの良いところに注目できていなかったか、ということに気づきました。
そのとき以来、私は《妻さん》や《娘さん》の良いところを、日記に記していくこととしました。また、《妻さん》と《娘さん》の映ったステキな写真を模造紙に張り、その余白にはそれぞれの良いところを書いて、自室の壁に貼ることとしました
DV・虐待をしていた私が見ていなかった「《妻さん》と《娘さん》の良いところ」は、二人が家から避難し、私がDV・虐待と向きあう中で、どんどん見えてくるようになりました。
例えば、《妻さん》は、笑顔がステキです、毎日を大切に生きています、感謝の心をいつも持って生きています、仕事も一生懸命です、チャレンジ精神があります、趣味が多彩です、一つ一つが丁寧です、創造性があります、優しいです、信頼できる人です…。
《娘さん》は、明るいです、自分の気持ちを素直に表現できます、おいしいものが好きです、モノを作るのが好きです、元気です、努力家です、発想が豊かです、楽しいことを見つけるのが得意です、幸せを表現できる人です、笑顔がいっぱいです…。
《妻さん》と《娘さん》の良いところを具体的に気づけるようになるほど、私は、「こんなに素敵な《妻さん》や《娘さん》にDV・虐待した自分は、やっぱり変わっていく責任があるのだ。そして、自分自身がDV・虐待をしない自分に変わる責任があるし、変わっていきたい!」との想いを強くし、一層前向きに加害更生プログラムに参加できるようになりました。
プログラムでも、自分自身がDV・虐待を手放すステップの一つとして、「パートナーや子どもに対する歪んだイメージを変えて、もっと肯定的で共感を伴ったものとすること」が重要であると学びました。それを実践することで、自分の学びを一歩前に進めていくことができたと感じています。
Ⅵ プログラムに通い始めてからの状況の変化
【離婚】
プログラムでの学びと並行して、離婚調停が始まりました。そして、約1年にわたる離婚調停を経て、離婚することになりました。
《妻さん》は初回の離婚調停の際に、私がDV加害更生プログラムに参加していることを初めて知って、驚いたそうです。そして、婚姻を続けるか離婚するか、悩んだようです。
その上で、数か月悩んだ後、数回目の離婚調停の際、調停委員さんを通して、「あなたは頭の回転が速い人だから、プログラムで学んだ内容は、すぐに頭では理解できるでしょう。でも、これまでのDV・虐待を踏まえたときに、本当に学んだ内容が日常生活の中で染み出してくるのか、実践できるのかと考えると、不安です。今はまだ、信じることができません。」という趣旨の言葉を伝えてくれました。
最初《妻さん》の言葉を聴いたとき、ショックもありました。「いっそのこと、全てを投げうって、逃げ出してしまいたい」という気持ちにもなりました。
しかし、一方で、「ここで逃げ出してはダメだ」という直観もはたらきました。今自分が、人生の岐路に立っている、と強く感じました。
私は改めて、《妻さん》の言葉を一層丁寧に思い返してみました。すると、《妻さん》が、調停委員さんを通して、「別れることで、自分を取り戻したい」という趣旨の言葉も伝えてくれていたことを思い出しました。
私は、自分が離婚を受け入れることは、《妻さん》が安心を感じられる最初の一歩になるのだと気づくことが出来ました。そして、「今すぐは難しいだろうけれど、いつかDV・虐待をせずに安心してコミュニケーションの取れるような、そんな自分に変わり続けたい」と前向きに離婚を捉えられるようになりました。
たとえ離婚した後も、元妻・元夫という関係は残ります。《娘さん》にとっての父親であるという事実も、消えてなくなることはありません。だから、離婚した後も、もし今度会う機会をいただいたときに、《妻さん》や《娘さん》にとってステキな自分であるために、変わり続けたい、という想いで、私は、離婚した後も、加害更生プログラムに通い続けることとしました。
ちなみに、もう一つ、私がプログラムに通い続ける選択をした背景として、離婚が決まる最後の調停の日に、調停委員さんを通じて、《妻さん》から、「たとえ離婚しても、プログラムには通い続けてほしいです。《娘さん》にとって、父親であることは変わらないので。《娘さん》にとって、良い父親であってほしいです。」という言葉をいただいたことがあります。
私はその言葉を聴いたとき、私が《娘さん》にとって、どのような存在でありたいか、と考えました。離婚したからと言ってプログラムをやめてしまえば、《娘さん》にとって私は、「虐待した父親」で終わってしまいます。しかし私は、そうなりたくありませんでした。「虐待をしたけれど、それを認め変わろうと努力し続けている父親」でもありたいと思いました。)
【離婚した後】
そして実際、「離婚して終わり」ではありませんでした。むしろ、そこからが本当の始まりでした。
〔《娘さん》との面会交流〕
まず、離婚してから、《娘さん》と月に1回の、面会交流が始まりました。
面会交流は、離れて暮らす親の一方が、定期的に会って交流するものです。私は、面会交流支援(当事者のみで面会交流が難しい場合に、その支援を行ってくれる団体があります)を行う第三者機関のスタッフが同席する下で、二人が家から避難してから1年数か月ぶりに、《娘さん》と会うことになりました。
初めての面会交流のとき、最初《娘さん》は震えていました。それは、緊張のためかもしれませんし、私の顔を見て、虐待されていた記憶がよみがえったからかもしれません。硬い表情をしていました。私もとても緊張しました。
プログラムでの学びを通して、私は、子どもも一人の人間として尊重される存在であることや、子どもの話に耳を傾けることが大切であることなどを学習しました。そこで私は、《娘さん》との関係の中で、こうしたプログラムで学びの内容を実践していくことを心掛けました。
例えば、DV・虐待をしていたときの私は、「自分が《娘さん》にさせたいこと」を優先していました。しかし、この時はそうではなくて、「《娘さん》がしたいこと」を優先するように心がけました。また、《娘さん》の発言に対しても、以前の私であれば「それは間違った考えだ」といって評価を下していました。しかし、面会交流中の私は、「《娘さん》はそう考えているんだね」と、評価を下さずに《娘さん》の気持ちをそのまま受けとめることを意識しました。
こんなふうに学びの内容を実践していく中で、《娘さん》の表情に、少しずつ笑顔が見られるようになりました。きっと《娘さん》の中で、「あれ、お父さんは前の暴力的なお父さんじゃなくなってきている」、「お父さんは、以前と違って、今は自分の話を聴いてくれる」という想いを抱くようになったのかもしれません。面会交流を重ねるにつれて、《娘さん》は、自らの気持ちをのびのびと表現してくれるようになってきました。
〔《妻さん》との手紙のやり取り〕
面会交流では、《娘さん》とは直接会うことになりますが、《妻さん》とは直接会いません。しかし、《妻さん》との間で、手紙のやりとりをさせていただけることになりました。面会交流の際に、《娘さん》が《妻さん》から私宛の手紙を届けてくれ、かわりに、私から《妻さん》宛の手紙を面会交流終了後に持ち帰ってくれる、というプロセスです。
《妻さん》との手紙のやり取りも、DV加害更生プログラムでの学びの内容を実践していくように心がけました。
以前の私は、「自分の気持ちを伝える」ことばかり優先していました。「手紙」でも、相手がどう受け取るかを考えず、一方的に自分の考えを押し付けていました。
でも、プログラムでの学びを踏まえて、改めて「手紙」の意味を考えると、そうではなくて、《妻さん》との言葉を介したコミュニケーションなのだと気づくことができました。
私は、まずは《妻さん》の気持ちを受けとめることを意識しました。《妻さん》が書いてくれた手紙を何度も読み返しました。そして、「《妻さん》は今どんなことに楽しい、うれしいを感じているのだろう」、「どんなことに、苦労を感じているのだろう」と想像してみました。それだけではありません。《妻さん》が「ハマっている」と手紙に記してくれた音楽があれば、それを聴いてみました。「ハマっている」料理があれば、自分も作ってみました。そうやって、《妻さん》のことを深く理解しようと心がけました。
その上で、「自分なら、どのような返事をもらったら、嬉しかったり、励まされたりするかな。」と想像してみました。何度も下書きをして推敲を重ね、次の面会交流までの1か月を掛けて、ゆっくり手紙を書いていきました。
こうやって、プログラムでの学びを活かし、《妻さん》への共感を高めていこうとする中で、少しずつ、《妻さん》がどんな言葉を必要としているのか、リアリティをもって想像できるようになりました。
そして、手紙のやりとりを重ねる中で、《妻さん》からも、気持ちのこもった温かいお手紙を沢山いただけるようになりました。そうした中で、《妻さん》は、「面会交流だけでなく、今度は《娘さん》を交えて3人で会いましょう」と言ってくれるようになりました。
〔3人での出会い〕
ある春の晴れた日、《妻さん》、《娘さん》と3人で会えることとなりました。約3年ぶりのことでした。
緊張もあったでしょうが、笑顔溢れる貴重な時間となりました。《妻さん》と《娘さん》はステキだなあ、一緒にいられることに感謝したいなあ、という気持ちで満たされました。
《妻さん》と《娘さん》も、たくさんの笑顔を見せてくれており、かけがえのない幸せな時間となりました。《妻さん》は私に対して、「DV加害更生プログラムに通ってくれてよかった。変わってくれてよかった。」という趣旨の言葉を掛けてくれました。本当にうれしかったです。
それから何度も、3人で会う機会をいただきました。会う機会を積み重ねる中で、3人で満ち足りた時間を過ごすことができました。そのうち今度は、《妻さん》と《娘さん》が住む家の近くに引っ越してもいいよ、ということになりました。
今は、二人が住む家から自転車で5分の距離に住んで、ほぼ毎日、一緒に過ごさせてもらっています。《妻さん》と《娘さん》との大切な日々を積み重ねる中で、少しずつ、信頼関係を築き始められるようになってきた、と実感しています。
もちろん、私がDV・虐待を犯したという事実が消えることはありません。《妻さん》や《娘さん》の記憶に今も残っていますし、そもそも、DV・虐待をなかったことにはできないのです。私は、自分が犯した行為の責任を果たしていく必要があります。
DV・虐待をしていた自分に逆戻りしないために、そして、《妻さん》や《娘さん》とより良い人間関係を築ける自分に変わり続けるために、これからも加害更生プログラムで学びを続けようと考えています。
Ⅶ おわりに
私が、DV加害更生プログラムでの学びを経て、今に至るのは、多くの方の支えがあったからです。《妻さん》、《娘さん》の存在のおかげで、私は学びを続けようと思えました。そして、プログラムで一緒に学ぶ仲間、プログラムの主宰者、面会交流のスタッフ、職場の同僚、友人・知人…。本当に多くの方の支えで、今の自分があります。
DV加害更生プログラムの仲間から教えてもらった言葉で、今の私の座右の銘になっている言葉があります。それは、「みんなに支えられて生きている」です。
これからもこの気持ちを胸に、プログラムで学び続けていきたいと考えています。
一般社団法人 Turn to Smile たんとすまいる
東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2F
MAIL:info@turn-to-smile.org
平日: 10:00~18:00
(面談時間 月・木・金:21:00)
土日祭日: お休み
※面談中のために応答出来ない場合がございます。
その場合は、お手数ですが改めてご連絡お願いいたします。